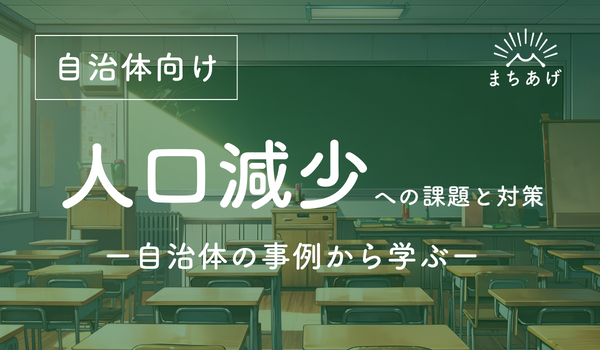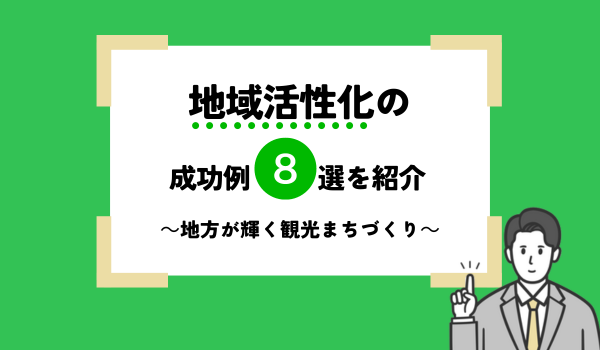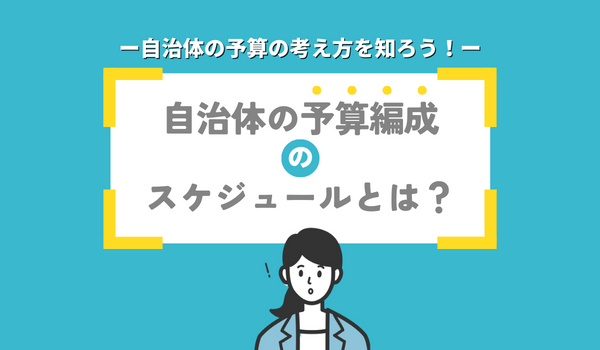観光プロモーションの手法と自治体の課題や成功事例を解説
%20(22).png)
まちあげパン太
まちあげの紹介から、WEBマーケティングに携わる方向けに、Web広告に関わる幅広いコンテンツをお届けします。
観光プロモーションとは、自治体などが観光地や商品・サービスなどを認知してもらい実際に旅行や商品購入を促すために実施する施策です。
自治体が観光プロモーションを具体的におこなう手法としては、広告や広報(PR)、セールスプロモーションなどが該当します。
観光プロモーションを成功させるには、観光客が求めている体験・ニーズや、購入したい商品を把握し、それに合わせたコンセプトやストーリーづくりが求められます。
さらに、観光客に伝えたい情報を効果的に伝えることも必要です。
この記事では、観光プロモーションの手法や成功事例をご紹介します。
自治体が観光プロモーションをおこなう際の課題や、押さえるべきポイントについても解説します。
最後に、観光プロモーションで活用できるサービス「まちあげ」についてご紹介します。
自治体の観光プロモーションご担当者は、サービス内容を理解してプロモーションを成功に導くための参考にしてください。
目次を表示
- 観光プロモーションの定義
1.1 なぜ観光プロモーションの取り組みが必要なのか
1.2 自治体が観光プロモーションで抱える課題とは
1.3 観光プロモーションの手法やポイントとは - 観光プロモーションをおこなう前に確認しておくこと
2.1 ターゲットとする旅行者を決める
2.2 旅行者が体験したいと思う内容
2.3 プロモーションをおこなう媒体 - 観光プロモーションをおこなう手法
3.1 動画
3.2 イベント
3.3 SNS
3.4 雑誌
3.5 広告 - 観光プロモーションで陥りがちな失敗とは
4.1 観光プロモーションにVTuberや萌えキャラを活用して失敗した事例
4.2 名産品の開発に成功し芸術祭を開催したものの長続きしなかった事例 - 観光プロモーション参考にしたい成功事例
5.1 有馬温泉・草津温泉の湯めぐりVR
5.2 大分県別府市「湯~園地」 - 観光プロモーションで押さえるべき2つのポイント
6.1 ターゲット毎にプロモーション方法を変化させる
6.2 プロモーションを継続しておこなう手法を考える - 旅行に興味関心を持つ層に広告配信できる「まちあげ」とは
- まとめ
観光プロモーションとは、観光客への観光情報の認知を拡大するためにおこなうプロモーションを意味します。
自治体や観光協会を始めとした観光関連団体が、地域の活性化を目的としてプロモーションをおこないます。
1.1 なぜ観光プロモーションの取り組みが必要なのか
観光プロモーションをおこなう目的は、地域の商品やサービスを多くの方々に知ってもらい、旅行や商品購入などの行動につなげることです。
地域の魅力を積極的に情報発信して、旅行や観光に訪れる方を増やすための観光プロモーションの取り組みを推進しましょう。
1.2 自治体が観光プロモーションで抱える課題とは
観光客の多くは、それぞれの地域の自然や文化などに価値を感じて観光や旅行に訪れます。
しかしここ数年、新型コロナウイルスの感染拡大により、長期間に渡って自粛生活が続いたため余暇の過ごし方や消費行動が多様化しています。リモートワークも推進され、メタバースなど観光に訪れる以外の楽しみ方が増えました。直接訪れなくても体験できるサービスも増えたため、実際に現地を訪れる観光の魅力が低下しているのは否めません。
ほかにも、自治体が観光プロモーションをおこなう手法として、地域紹介をする冊子の割合が高いことも課題です。これは、インターネットが広く普及している現代において、実情に沿ったプロモーション活動が展開されていないことを意味します。
スマートフォンが1台あれば、知りたい情報をすぐに獲得できる時代です。観光客が求める情報を届けるには、観光情報誌やメディア広告だけでは十分とはいえません。観光プロモーションをおこない成果を収めるには、観光客のニーズに合わせて訴求する必要があります。
1.3 観光プロモーションの手法やポイントとは
自治体が観光プロモーションをおこなう手法を設定する際に、有効なフレームワークを2つ紹介します。
- ・AMTUL
- ・ZMOT
「AMTUL」はAwareness(認知)、Memory(記憶)、Trial(試用)、Usage(本格的使用)、Loyalty(ブランド固定)の頭文字を取った消費者の購買行動モデルです。AMTULは観光プロモーションのように、観光や旅行を検討しているユーザーの長期的な態度変容に有効なフレームワークです。
AMTULで定量化する指標はそれぞれ以下の通りです。

- ・Awareness(認知):再認知名率
- ・Memory(記憶):再生知名率
- ・Trial(試用):使用経験率
- ・Usage(本格的使用):主使用率
- ・Loyalty(ブランド固定):今後の購買意向率
5つのうち「A: 再認知名率」とは、ブランド名を挙げると商品やサービス内容を認知できるかどうかを測るものです。
「MA: 再生知名率」とは、ブランド名を記憶しているかを指標とします。
「U: 主使用率」とは、そのブランドを日常的に使用している消費者の割合です。主使用率が高いということはブランドの認知が広まっており使用率が高いことを意味します。
AMTULのフレームワークを活用すると、ユーザーが商品やサービスを購買したタイミングや心理状態、リピートの可能性があるのかなどを可視化して戦略を立てることが可能です。
ほかにも重要な指標として、「ZMOT」(Zero Moment of Truth)も挙げられます。ZMOTはGoogleが提唱したマーケティング理論です。顧客は店頭に訪れる前にインターネットで情報収集してすでに買うものを決めているというマーケティング理論です。
自治体の観光プロモーションにおいて、観光施設や名産品を紹介することは一般的です。しかし、観光プロモーションで重要なのは、実際に訪れる方が得られる体験価値を伝えることです。
観光庁の『訪日外国人消費動向調査』や、訪日外国人の消費動向によると、日本に2回以上訪れている外国人観光客は61.6%にのぼるという結果が出ています。従来の商品・サービス自体に価値を見出すモノ消費から、体験・経験の価値を重視するコト消費へと遷移しています。
自治体がおこなう観光プロモーションでは、直接訪れることで得られる体験価値をアピールすることが求められるでしょう。体験価値をアピールするために動画でPRを作成する自治体も少しずつ増えてきました。
観光プロモーションをおこなう前に決めておくべきことがあります。旅行客により目的や求める体験価値は異なり、旅行に関する情報を取得する媒体も様々です。観光プロモーションを成功させるために、事前に確認しておくべき内容を理解しましょう。
2.1 ターゲットとする旅行者を決める
観光プロモーションをおこなうには、まずターゲットとする旅行者を決めることが大切です。狙うべき旅行者はカップルなのかファミリーなのか、あるいは外国人なのか、ターゲット層は細かく決めましょう。
ターゲット層をしっかり設定しないと、ユーザーの心をつかむようなプロモーションはできません。地域と親和性の高い旅行者のターゲットを絞り込むと、プロモーションの方法も自ずと決まってきます。
2.2 旅行者が体験したいと思う内容
モノ消費からコト消費に移り変わっているため、施設やサービスのアピールのみではプロモーションの効果はあまり期待できないでしょう。旅行者が思い出として持ち帰りたくなるような、直接その地域を訪問しないと得られない体験の内容を検討する必要があります。
2.3 プロモーションをおこなう媒体
自治体がおこなう観光プロモーションには様々な手法があります。狙うべき旅行者層を明確にし、そのターゲット層が興味関心を持って情報収集をする媒体を活用してプロモーションをおこなうのが最適です。
観光プロモーションをおこなう手法として、以下の5つが挙げられます。
3.1 動画
動画は観光プロモーションにおいて効果的なツールです。SNSや自治体のWebサイト、YouTubeなどの動画共有サービスで配信することで、多くの方に視聴してもらえる可能性があります。アピールしたい部分をストーリー仕立てにしたり、地域のユニークな取り組みを紹介するなど、しっかり作り込むことで視聴した方に強い印象を与えることができるでしょう。
3.2 イベント
全国各地でおこなわれる物産展やグルメ展に参加したり、イベントを開催したりするのも有効な手段といえるでしょう。観光客は直接訪れる前に地域の魅力あるコンテンツを体験できるので、今後の来訪も期待できます。
自治体独自にイベントを開催する以外に、複数の自治体が集まるイベントに出展する方法もあります。規模の大きいイベントはそのぶん来場者も増えるので、潜在顧客に知ってもらうきっかけを増やせるでしょう。
3.3 SNS
近年、SNSを利用しているユーザーも増え、それにともなってSNSアカウントの運営をおこなう自治体や企業も多く見られます。観光プロモーションとSNSは親和性が高いので有効活用しない手はありません。画像や動画を中心にビジュアルで訴求できるInstagramを用いて、集客を伸ばしている自治体や観光地が増えています。
10代〜30代は情報収集の手段として、SNSを積極的に活用しており、Instagramなどの写真や動画を元に旅行先を検討する方も多数います。利用者の多さと、その拡散性の高さからSNSは観光プロモーションに適した媒体といえるでしょう。
3.4 雑誌
雑誌を購入するユーザーは掲載する内容によって細分化されているため、ターゲットを絞り込みやすいメリットがあります。ターゲット層が読む雑誌に情報を掲載すると、狙いたいユーザーにピンポイントで情報を届けられます。
3.5 広告
広告は大きく以下の4つに分けられます。
- インターネット広告:Webサイトや検索エンジンを活用した広告
- マス広告:テレビ、新聞、ラジオなどマスメディアを活用した広告
- SP広告:デジタルサイネージ、交通広告、カタログなど、販促を目的とする広告
- SNS広告:SNSを活用した広告
それぞれの広告によってメリットもデメリットもあり、費用も変わります。観光プロモーションにおいて、これらの広告の中でもインターネット広告は重要です。インターネット利用率が8割を超える現在、観光や旅行を検討しているユーザー層は、基本的にネットを利用して観光情報を収集します。それゆえ、ユーザーが閲覧するSNSやWebページに掲載されるインターネット広告は効果的だといえるでしょう。
各地の自治体は、観光地に誘客するために観光プロモーションを積極的におこなっています。ただ、熱い思いを持って観光プロモーションをおこなっても、失敗してしまうケースも見受けられます。観光プロモーションを成功させるには失敗事例から学ぶことも重要です。
4.1 観光プロモーションにVTuberや萌えキャラを活用して失敗した事例
地方自治体でおこなった観光プロモーションの中で、観光大使や萌えキャラを作成して失敗してしまった事例を紹介します。
ある自治体が、バーチャルキャラクターを観光大使に任命して、SNSを通じPRを開始しました。その際、使用したハッシュタグに性別や容姿にまつわる内容が書かれていたため、問題視されました。
イラストやアニメーションなどを活用した観光プロモーションは全国各地でおこなわれています。萌えキャラを活用した観光プロモーションが成功している事例もありますが、一歩間違えると炎上につながるリスクがあることがわかる事例です。
4.2 名産品の開発に成功し芸術祭を開催したものの長続きしなかった事例
補助金に頼らない地域づくりを目指し、数々の名産品の開発に成功し多くの産業を作り上げた自治体があります。これにより、財源の確保に成功し地域は再生し黒字化を果たしました。
この自治体は黒字化した財源をもとに芸術家を招いて文化祭を開催。しかし、地域住民の中には自分達の価値観とギャップのある芸術家の言動を受け入れることができない方が多く、文化祭の規模は年々縮小されました。
地域の活性化を目指しイベントを開催したものの、地域住民の理解を得られずに失敗してしまった事例です。
各自治体が積極的に観光プロモーションをおこない、認知度の拡大や集客の増加につながる成功事例も増えてきました。
観光プロモーションの成功事例をご紹介しますので、プロモーションを検討中の自治体のご担当者はぜひ参考にしてください。
5.1 有馬温泉・草津温泉の湯めぐりVR
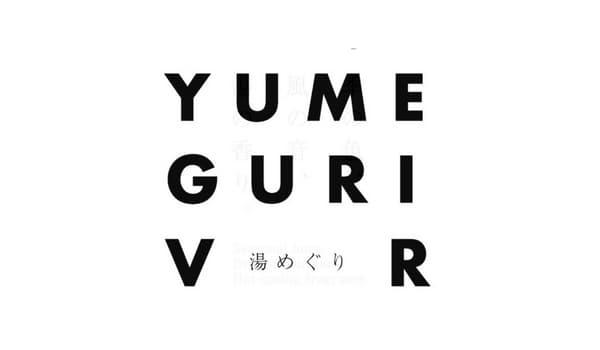
「湯めぐりVR」は、草津温泉と有馬温泉の日本を代表する2大温泉地が協力して、温泉が本来持っている癒しの力を発信するために、温泉入浴のVR動画配信を始めました。
4K対応のVRゴーグル等を装着して自宅で入浴すると、さながら温泉に入浴しているような映像をリアルに体感できます。
5.2 大分県別府市「湯~園地」

大分県別府市では、少し変わったPR動画を制作し配信しています。実際には存在しない遊園地と混浴施設を一緒にした施設を「湯~園地」と紹介しているユニークなPR動画です。
100万回再生されたら実際に混浴施設を作ると公言しており、たった3日間で100万再生を達成し大きな反響を生みました。その後3日間限定で「湯~園地」をオープンするなど、観光のプロモーションに成功している事例です。
自治体が観光プロモーションをおこなううえで大切なのは、ユーザーが情報を収集したあとに口コミやSNSで拡散してもらうことです。観光プロモーションの情報を届けたユーザーが、地域に対し興味関心を持ちファンになってくれると、情報を拡散してもらいやすくなるでしょう。
ここからは、自治体が観光プロモーションをおこなううえで、押さえるべき以下の2つのポイントについて説明します。
6.1 ターゲット毎にプロモーション方法を変化させる
まず、観光プロモーションをおこなう前に、ターゲットとするユーザー像を明確にしましょう。日本人向けなのか訪日外国人向けなのかによってもプロモーションの手法は大きく変わります。現代は、SNSや動画共有サービスなど様々な手法を用いてプロモーションをおこなえるため、何を取り入れたらよいのか迷う自治体が多いかもしれません。
日本語が分からない外国人観光客に向けてのプロモーションとして、動画で視覚的に情報を提供する方法も有効です。その際、動画に英語字幕を付けて制作することも必要です。ターゲットとするユーザー層が若年層の場合は、SNSを活用したプロモーションが効果的でしょう。
自治体として観光プロモーションにかけられる予算を元に、ターゲット毎にプロモーションの内容を変化させましょう。
6.2 プロモーションを継続しておこなう手法を考える
自治体で観光プロモーションをおこなう際に失敗する理由の一つとして、プロモーションを継続できないことも挙げられます。動画の視聴回数が伸びてプロモーションに成功したと感じると、結果に満足してしまい、継続できずに終わってしまうこともあります。
多くの自治体が最初の段階では新しいことにチャレンジしようとしますが、その後の継続は難しいものです。一度の成功に満足せず、アプローチを継続してプロモーションの効果を高めることが大切です。
自治体が観光プロモーションをおこなう際、旅行・観光をしたいと考えているユーザーを絞り込む方法が課題の一つといえるでしょう。
年齢・性別・居住地などで観光客のターゲット層を絞り込めたとしても、その地域に興味や関心があるとは限らない点が懸念されます。
自治体が観光プロモーションを成功させるには、その地域を観光したいと考えているターゲットユーザーに広告を届ける必要があります。
マイクロアドが提供している「旅行でまちあげ」は、観光客を増やしたい自治体に適したマーケティングプロダクトです。
マイクロアドが保有しているオーディエンスデータと、連携している外部データを掛け合わせ導き出した結果から、自治体のプロモーションに興味を持つユーザーに合わせた広告配信をサポートしています。
ターゲティングの設定例は以下のとおりです。
|
ターゲット層 |
旅行に興味のある層 |
|
行動履歴 |
年末年始 or お盆などに〇〇に旅行した人 |
|
位置情報 |
隣県に居住している方 |
その地域への旅行に興味関心のあるユーザーを絞り込んだ状態で広告配信できるので、広告をクリックされる確率は高いといえます。
本記事では、観光プロモーションの具体的な手法と押さえるべきポイントや成功事例を紹介しました。観光プロモーションで大切なのは訴求したいターゲット層を明確にし、プロモーション手法を絞り込むことです。
自治体で観光プロモーションをおこなう際に「まちあげ」を活用すると、観光や旅行に関心のあるユーザーに向けて広告配信が可能です。
費用対効果の高い観光プロモーションをおこなうためにも「まちあげ」をぜひご活用ください。
.png?width=500&height=115&name=logo_machiage_500_l%20(1).png)








%20(500%20%C3%97%20500%20px).png?width=500&name=%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%20(500%20%C3%97%20550%20px)%20(500%20%C3%97%20500%20px).png)
%20(500%20%C3%97%20500%20px)%20(1).png?width=500&name=%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%20(500%20%C3%97%20550%20px)%20(500%20%C3%97%20500%20px)%20(1).png)